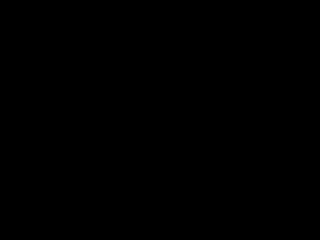
かなり間が空いてしまったが、ゲームのことを語ろうと思う。
「月1くらいで書こうかな」と言っていたわりには3ヶ月も経ってしまった。
楽しみにしていてくれた方に対しては、ほんとうに申し訳ない。
正直、時間的にも精神的にも、かなり余裕がないと書けないことがわかった。
過去のことを語るなんて、あまりしないことなので、それなりのものを
しっかり書こうと思っているうちに、ずいぶん時間が経ってしまった。
というか、やっぱり過去のゲームのことって、精神的にも大変なものである。
……って、申し訳ないとか言っておいて、申し訳しているね。
すいません……。
さて。
前回も書きましたが、ゲームの紹介をしたいわけではないので
内容に関することは、まったく語りません。
あと、ここに書いてあることは、特に重要なこと、というわけでもありません。
いま、思い出すことを、順番も関係なく、語ろうということ。
語り続けていたら、いくらでも語っていられる。
どの作品も、いろんな思い出があるし、一生懸命作っていたからね。
2回目となる今回は、『リアルサウンド 〜風のリグレット〜』。
夏が舞台のゲームを、こんな時期に語るのもどうかと思ったけど
「さて、いま、なにを語ろう?」と思ったら、このソフトが浮かんだので
『リアルサウンド 〜風のリグレット〜』について、語りたいと思います。
この作品も、いろんな面から語ることができるけど
たまたま数日前に、大きな広告で笑顔を見たので、彼女のことから語ろうかな。
この作品の女優、菅野美穂さんのこと。
いまもあまりテレビは見ないが、当時はいまよりも見ていなかったので
仕事をする前、僕は、菅野美穂という人を、失礼なことだが、知らなかった。
もう1人のメインの女優として頼んだ、篠原涼子さんのことは知っていたんだけど。
「誰に出ていただこうか?」ということになったとき
僕に、あまりに女優についての知識がなかったので、ビデオを何十本も見ることになった。
その中で、いい演技をしている人、いい声をしている人を探そうということだ。
もちろん、早送りしたり、「はい次」なんてやりながらだけど。
画面がない、声だけのゲームであるから、画面を見ずに、声ばかりをいっぱい聞いた。
何十本目か忘れちゃったし、その作品の名前も覚えていないんだけど
「絶対にこの人だ!」という女性を発見した。それが菅野美穂だった。
抜群に演技、その声が飛び込んできた。
しかし、その人の名前がわかる方法がなかった。役者の名前が表示されるわけでもないし。
主役でもなかったので、エンディングのスタッフロールを見てもわからなかったので
ビデオを指さして「これ誰?」と聞いて、やっとわかった。
最初にお会いしたときは、オフィスに来ていただいて、作品の説明をしたとき。
そのとき、なんでか知らないけど、僕は紙パックのイチゴミルクを飲んでいた。
イチゴミルクなんて、2年に1回飲むか飲まないか、くらいなんだけど。
彼女が部屋に来るちょっと前に、僕はイチゴミルクのパックを倒してしまって
机の上がイチゴミルクだらけになって、慌ててふいているところに彼女が入ってきた。
当たり前のように、大爆笑だ。
一緒に何日も仕事をしてみて、彼女のすごいところは、山ほどあったが
仕事というか作品への取り組み方が、半端無かった。
仕事の初日に、台本というか作品全体を、しっかりと頭に入れてきたのは彼女だけだった。
というのも、声の収録だから、役者は、台本を目の前に置いて演技ができるのである。
映画やドラマだったら、台詞を覚えてくる必要があるが、その必要はない。
何度か読み込んでいただいて、ぼんやりと台詞を覚えて来ればそれでOKだった。
しかし、彼女は違った。作品を、台詞がどうこうではなく、しっかり頭に入れてきた。
初日の最初は「ここはこういう理由で、この台詞なんですよね?」と、質問攻めにあった。
とても感心した。感動した。この人に頼んでよかったと、心から思った。
彼女の演技は天才だと思うが、同時に非常にプロであった。
ちなみに、誰とは言わないが、まったくプロ意識に欠けた人たちがいた。
役としては、ちょっとした役ではあったが、ぜんぜん気持ちが入っていなかった。
収録を初めて、すぐにわかった。同じ事務所から来た役者たちだった。
僕は激怒して、全員、帰らせた。
「ギャラはぜんぶ払うが、使わない! ふざけるな!」と、その事務所の社長に連絡した。
やる気がない人、仕事を楽しめない人とは仕事をしない。
それはいまもずっと変わらない姿勢だ。
菅野美穂の、エピソードを1つ語ろう。
1つのエンディングのシーンで、彼女が泣いて泣いて泣くシーンがあるのだが
1カット15分くらいあるので、収録が大変だった。編集はしたくないし、できないし。
普通のシーンでも大変なのに、大泣きするシーンである。
彼女が1人で喋るシーンなので、小さな部屋に1人おいて、孤独な状態にして収録した。
最初のテイクが収録終わったとき、残念ながら、僕はちょっと演技が満足できなかった。
様子を見に行くと、シャツの色が変わっていて驚いた。
声も枯れていた。声の収録だというのに、全身で演技をしたことがよくわかった。
あまりの本気の演技だったので、すぐに次のテイクが収録できない。
休みながら、彼女に演技の指示を与えた。
しばらく休んでから、次、また次と、テイクを繰り返した。
時間も遅くなってしまったし、精神的にも体力的にも限界だろうし
それまででは一番よいテイクが録れたので、「OK」を出した。
「OK」を出したところ、彼女がつっかかってきた。
満足ができない。もう1度やろうと。
このときの彼女の顔は、ずっと忘れられない。
ほかにもいっぱい、感心したり、感動したり、驚いたエピソードはあるのだが
彼女も、こんなことをいまさら語られるのもいやかもしれないので、これくらいで。
『菅野美穂のことを語ろうか』になっちゃうし。
当時まだ、10代ですよ。驚き。
翌年、ヌードの写真集を出したときは、なんとも複雑だった。
僕がその写真集を見ることができたのは、しばらく経ってからだったが
僕が渡した、『リアルサウンド』のシャツを着た写真があって、とても嬉しかった。
って、こんな調子で語っていたら、終わらないな。
次に思い出したことを、順番に語ろう。
この仕事を通して、もっとも驚いたのは、脚本のレベルの高さだった。
脚本を読み終えた、その瞬間が、もっとも驚いたときだった。
脚本を書いてくれたのは、坂元裕二だ。
彼の脚本が上がったとき、僕はなにかの予定で、遠くまで電車で出かける用事があった。
ちゃんと読むべきだと思ったのだが、電車の中で時間があったので
パラパラと読み始めたら、気付いたら、読み終わっていた。
電車を降りて、すぐに「素晴らしい!」と、彼に電話した。
読んでいる最中、僕は、電車の中にいたわけだが、電車の中にいなかった。
完全に作品の世界の中にいた。
読み終わって、自分が電車の中にいることに気付いた。それくらいだった。
この作品は、画面のないゲームである。
自分がどこにいるのか忘れさせてくれるくらいの脚本だったわけで
「この作品には、もう、これしかない!」と心から感じた。
周りが見えなくなってくれるような脚本でないと、困るわけである。
そして、この作品は、音だけのゲームであるが
音だけのゲームだからできること、が脚本でなければつまらないのである。
つまらないというか、存在価値が、ちょっと薄くなってしまう。
そんなことも、言わずとぜんぶ理解して、最高の脚本を作ってくれた。
もう1つ言うと、画面がないから、場面転換が大変なのである。
Aというシーンから、Bというシーンに来たとき、舞台が変わっていたら
映画だったら、映像の変化ですぐにわかるが、それができない。
とはいえ、「ここはBだね」なんていう台詞はよろしくない。
かといって、小説のように、説明もできない。
そんなことを、見事にやってくれた。
やってくれただけではなく、作品の価値に仕上げてくれた。
彼と出会っていなかったら、「画面がないゲーム」、「音だけのゲーム」という
ただの「意欲作」で終わっていたと思う。
坂元裕二という人は、人間も素晴らしい人で、彼といると明るくポジティブになる。
仕事をしていただいているわけだが、それ以外に得るものがいっぱいあった。
「坂元さんと会った後は、あんた楽しそうやなあ」と、カミさんに言われるくらいだった。
彼にいつかまた、仕事してほしいなあと心から思っている。
最近、なぜか、とくにそう感じている。
この作品の音楽を作ってくれたのは、鈴木慶一さんだ。
たぶん、外部の人で一番最初にこの作品の構想を語ったのは、慶一さんに対してだと思う。
鈴木慶一さんが、ぴったりだと思ったのである。
正直言うと、こんな「音しかないゲーム」なんていう作品の音楽は、自分が作りたかった。
単に良い曲が作れるというだけではなく、作品のことをしっかり理解してくれないと
「音しかないゲーム」の音楽は作れない、というのもあった。
映画以上に、音楽で、ドラマやシーンを語る必要があるからである。
しかし、彼の音楽が頭で鳴った。だから、作品の制作が本決まりになる前だというのに
彼に構想を打ち明けた。彼が興味を持ってくれたので、彼に頼もうとそのとき思った。
驚いたといったら、失礼かもしれないが、鈴木慶一という人は
ものすごく丁寧に、一生懸命、仕事をする人だった。
この作品の音楽を作っている期間、スケジュールをずっと空けてくれた。
朝から晩まで集中して、ずっとずっと良い音楽を作ってくれた。
いまでも、感謝したいくらい、ありがたいことだ。
そんな慶一さんに対しての、僕のお返しは、アビーロードでのレコーディングだった。
ある日、慶一さんに「この作品は、アビーロードでレコーディングします」といったとき
「アビーロードでやるの!?」と驚いて、ちょっとニコっと笑ってくれたことを思い出す。
彼との仕事の現場で思い出すことがある。
最初は、東京のスタジオで何日もかけて、音楽を作っていたのだが
僕も、ほかの仕事をぜんぶやめて、ずっと現場で付き合うことにした。
プロデューサー兼監督が、音楽の制作現場に最初から付き合うなんて珍しいことである。
初日、スタジオに行ったが、当たり前だが、なにもすることがないのである。
ずっと、ずっと、何時間も。終わるまで。夜まで。
たまに意見を求められるので、返すくらいで。
2日目も同じだった。
音楽の現場だから、なにもやることがない。ほんとに当たり前なんだけど。
ずっとソファに座って、意見を求められるのを待つくらいだった。
2日目が終わろうとしたとき、僕はあることに気付いた。
唐揚げが……ない……。
スタジオに差し入れをいろいろ持っていったのだが、その中に唐揚げのパックがあった。
唐揚げがいっぱい入ったパック、たぶん5人前くらいを差し入れに持っていたのだが
気付いたら、自分でぜんぶ食べていた。昼から夜までかけて、ぜんぶ。
することがないから、ソファに座って、ずっと唐揚げを食べていたわけである。
それがもう、なんとも言いようがないショックで、僕はソファから立って、慶一さんに
「僕、今日いちにちで、この唐揚げをぜんぶ食べてしまいました」と伝えた。
それだけのことなのに、僕の気持ちを、その一言で、すべて慶一さんは理解してくれた。
次の日から、僕も音楽制作に加わることになった。
慶一さんと一緒になって、音楽をいっぱい作った。
思い出すのは、慶一さんという人は、よく寝る人だということ。
スタジオで慶一さんが疲れて眠ってしまったとき
起きるまで待っていようと、僕が『MOTHER』の曲をポロロンと弾いていたら
突然ガバっと起きあがって、慌てていた。
どうしたのかと尋ねると、間違って同じような曲を作ってしまったかと思った
ということだった。
とてつもなく、面白い。
別の日のこと。また慶一さんが疲れて眠ってしまったことがあって
その頃は僕も溶け込んでいたので、勝手に1曲、慶一さんのメロディを元に作り上げた。
やがて慶一さんも起きて、次の曲。そのままレコーディングも進んで、終わった。
上がった曲を聞き返す中、慶一さんも、「この曲いいなあ」と言ってくれていた。
ちなみに、その曲は、主役の柏原崇くんが、もっとも気に入ってくれた曲である。
仕事が終わってしばらくしてから、なにかのメディアで対談することがあって
僕が勝手に作り上げた、その曲のことを話題にすると、慶一さんが驚いていた。
どうしたのかと尋ねると、ずっと、いつ作ったのか思い出せない曲があった
ということだった。
僕は伝えたつもりだったが、慶一さんは、ずっと謎だったそうである。
「そうか。そうだったんだ……。やっとわかった……」と言っていた。
とてつもなく、面白い。
……えーと。
いつの間にかずいぶん長くなってしまった。
語るべきことを、語っていないような気がするなあ。
いま気付いたが、いっぱいあるぞ。
音のミックスで苦労した話も、してないなあ。
イベントもやったしなあ。
エンディングに矢野顕子さんの「ひとつだけ」を入れるための
エピソードだけでも……と思うが、そろそろ終わりにしよう。
だけど……、最後に、これは語っておこうかしら。
この作品は、普通に作品として、制作、販売する以外に、1つ大きな目的があった。
それは、視覚障害を持った人たちに、遊んでもらうことである。
そんなことを思ったのは、視覚障害を持った方からもらった手紙がきっかけだった。
視覚障害を持った人たちもゲームはプレイするということだった。
実際に、何人かにお会いして、話も伺った。
音を頼りにして、格闘ゲームでもなんでも、プレイするのである。
考えたこともなかったので、驚いた。
そういう話を聞いたとき、ゲームの作り手として、考えるものがあった。
また、視覚障害を持ったの人たちに向けたゲームというものは存在する。
しかし、そういうゲームは、視覚障害を持たない僕たちは遊ばない。
だから、その間で、コミュニケーションは生まれないのである。
僕が思ったのは、ゲームをプレイした後
視覚障害を持った方と、持っていない方で、コミュニケーションが生まれる
そんなゲームが作ってみたい、ということだった。
同じ感想を持つ、そんなゲームが作ってみたい、ということだった。
もちろん、それだけが制作の理由ではない。
以前から、音がメインのゲームを作りたいとは思っていたし
坂元裕二とも仕事がしたかった。
『Dの食卓』や、『エネミー・ゼロ』で、「CG、CG」と言われ続けるのがいやだった。
だけど、かなりの挑戦となる、「画面のないゲーム」を
実際に制作しようと、動くきっかけになったのは、そんな思いだった。
とても印象的だったことがある。
この作品は、セガのサターンというハードで登場したのだが
サターンに独占提供するかわりに、ハードウェアを1000台寄付していだく
僕らはソフトウェアを1000本寄付するので……という無理な提案をした。
趣旨を理解していただき、OKをいただいて嬉しかった。
ゲームができて、しばらくした後
視覚障害を持った方々、数人から感想を聞く機会があった。
正直に言うが、僕は、感謝されると思っていた。
ほんとに、偉そうなもんだ。
偉そうで申し訳ないが、そう思っちゃっていた。
「このようなソフトを作っていただいて……」なんて言われると、どこかで思っていた。
しかし、まったく違った。
まったく、普通のゲームプレイと同じような感想だった。
「ここはもっとこうしてほしかった」など言われた。
「ここがよくない」とも言われ、怒られてしまった。
もう一度言うが、僕は
ゲームをプレイした後、視覚障害を持った方と、持っていない方で
コミュニケーションが生まれる、そんなゲームが作ってみたい
という思いで、この作品を作ったのだ。
同じ感想を持つ、そんなゲームが作ってみたい、と思っていたのだ。
ずっと、ずっと、涙が止まらなかった。
嬉しくて、嬉しくて。
作ってよかったと、そのとき、心から思った。
Tweet